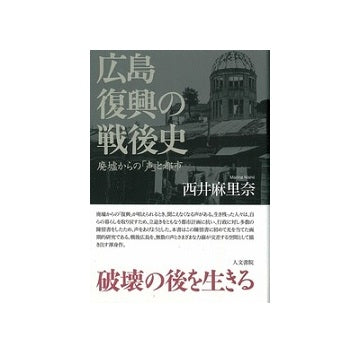
広島 復興の戦後史 廃墟からの「声」と都市
廃墟からの「復興」が唱えられるとき、聞こえなくなる声がある。生き残った人々は、自らの暮らしを取り戻すため、立退きをともなう都市計画に抗い、行政に対し多数の陳情書をしたため、声をあげようとした。本書はこの陳情書に初めて光を当てた画期的研究である。戦後広島を、無数の声とさまざまな力線が交差する空間として描き出す渾身作。
「廃墟をどうにか手なづけようとする無数の試みが交錯し、ぶつかり合う場所に、歴史、社会、都市、そしてそこに生きる人びとの姿が立ち現れる。この街で、人びとが生きて住むために、苦難を訴え、ときにより良く暮らすための狡知を含みながら語った言葉が、今や失われた街や、戦後日本社会の路地裏へと、私たちを誘う。そして破壊されたこの街は、複数の声がぶつかり合うなかで、もう一度「広島」になり、今に至る。ならば、広島はいかに復興してきたのか。」(本書より)
■目次
・序章
先行研究と本書の位置づけ
本書の対象と方法
本書の構成
・第1章 廃墟と描線 都市復興のなかの境界画定
戦災復興土地区画整理事業の開始
異議申立ての声 陳情書の考察・七つの視点から
廃墟と描線
・第2章 死者の都市 移動する墓碑の軌跡
死者と都市
復興事業と墓碑移転 誓願寺と川内村義勇隊
適正化される空間 都市の復興と死者
・コラム1 働いた者の手 復興の空間経験
・第3章 顕在化する復興の境界線
一九五〇年代、都市の住宅復興
分岐する住まい 引き続く戦災の影響
立退きの延期を求める声
陳情書と都市 境界侵犯/画定の発話行為
・第4章 禁じられた復興を生きる 広島平和記念公園
公園に住む人びと
記念空間の形成と立退き
原爆ドームを見上げる街
・第5章 「不法占拠」という復興経験 一九七〇年・相生通り調査から
「相生通り」調査の同時代
個人史のなかの調査経験
「いえ」がつくる「まち」
「基町のおと」の言葉のゆくえ
調査から記録へ 調査経験の再定位
・コラム2 波紋を呼び寄せる 「相生」から現代美術館へ
・終章 廃墟のなかの「声」を読みとく
著者:
出版社:人文書院
サイズ:四六
ページ数:380
発行年:2020.04

