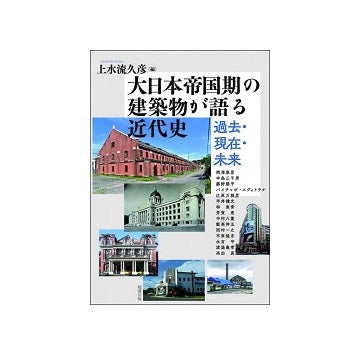
大日本帝国期の建築物が語る近代史 過去・現在・未来
これまで「負の遺産」とされる傾向にあった大日本帝国期の建築物は、近年一部の地域ではカフェやホテルに変貌し、なかには歴史遺産に認定されたものもある。
こうした変化は何を意味しているのか。そもそも、これらの建築物はなぜ、どのように建てられ、帝国崩壊後はいかなる歴史を歩んできたのか。また、現在は現地でどのように位置づけられているのか。
建築時の状況、植民地支配に果たした役割、保存や破壊をめぐる政治、歴史遺産への認定、現在の活用実態など、植民地建築をめぐる多様な問題を、文化人類学、建築学、観光学、建築史、思想史、メディア学など多角的視点からよみとく。
歴史的建築物を過去の遺物としてではなく、ひとびとの価値観や歴史認識を映し出す鏡としてとらえ、旧植民地への理解や今日のアジアと日本の問題を考える手がかりを示す。
■目次
序言 大日本帝国期の建築物が語る近代史 過去・現在・未来
I. 大日本帝国期の建築物を俯瞰する
東アジアにおける日本の支配と建築
大日本帝国と海外神社の創建
旧植民地の建築物の現在 多元的価値観の表象
II. 大日本帝国に建築物を刻む
帝国が残した国立博物館と戦後の社会
帝国日本の南北に建設された製糖工場と社宅街
開拓と宣教のせめぎ合い 北海道のキリスト教建築にみるまなざしのポリティクス
樺太期の「産業」の遺構は何を伝えるのか
III. 大日本帝国期の建築物を利活用する
「満洲」日本統治期の建造物の今 満洲映画に映された中国東北地方の建造物を中心に
監獄博物館とノスタルジア―ダークツーリズムを暗くするもの、明るくするもの
紅楼の現在 台湾社会の写し鏡の場としての歴史遺産
「日本」と「近代」を観光化すること 韓国・九龍浦の事例から
帝国医療の想起と忘却 旧南洋群島の病院建築物から
台湾東部における神のいない「神社」
東アジアにおける建築系産業遺産の保存と活用
IV 大日本帝国期の建築物を保存する/破壊する
市庁舎は誰のもの? 国登録有形文化財・大牟田市庁舎をめぐる事例より
沖縄の近代の語られ方 沖縄戦で消えた建築物
台湾の日式建築を残す人びと 何を想い、いかにたたかったのか
近代化と戦災の記憶を残す 旧広島陸軍被服支廠をめぐって
著者:上水流久彦
出版社:勉誠出版
サイズ:A5
ページ数:248
発行年:2022.02

