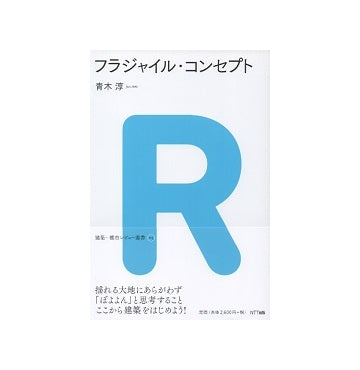
フラジャイル・コンセプト
「原っぱ(=人々が行動することによって楽しさを発見する空間)」と「遊園地(=人々の楽しみ方があらかじめ与えられている空間)」というコンセプトを提唱し、原っぱのような建築をつくることを試みてきた青木淳が、2011年の東日本大震災以降にさまざまな媒体に書いてきた原稿を中心に、テーマごとに並べ替えた論集。
そのなかから抽出されたアイディアを「フラジャイル・コンセプト」と名づけ、青木建築の新たなキーワードとして提出。震災以降の青木の建築への取り組み方の変化、息遣い、さらに今後の展望が描かれた一冊。
■目次
巻頭口絵 ぼよよん
序 フラジャイル・コンセプト
第1部 表現でないこと
1 「くうき」を整える
2 どこからが絵なのだろう、どこまでが絵なのだろう
3 谷崎的建築観vs 芥川的建築観
4 様相が内部空間の構成を食い破るとき-村野藤吾の現代性
5 キャンパスノートの使い方
第2部 東日本大震災
1 震災の日のこと
2 自分たちで環境をつくる
3 長清水のこと
4 代理を前提にしないデザイン
5 震災から半年
6 東日本大震災と関東大震災-今和次郎のこと
7 震災から三年-無防備の先にあるもの
第3部 具象と抽象を行き来しながら
1 建築とは建築の裏に隠れた秩序のあり方であり、模型はその秩序を指定する
2 なぜ、それを模型と呼ぶのか-石上純也さんのこと
3 「くうき」を伝える、「くうき」のような生き物-安東陽子さんのこと
4 〈作為〉-〈作者〉=〈ストーリー〉-トラフのこと
5 具象と抽象をどう折り合わせるか-ムトカのこと
第4部 日常の風景
1 少しずつ奥が見えてくる
2 すべての建築は道から進化した
3 毎日の行ないがつくる道
4 どこもが「寝室」になる
5 この場所で現実世界がほころびはじめること-ライアン・ガンダーのこと
6 複製することの魔法-ルイジ・ギッリのこと
第5部 建築を見ながら、考えたこと-『新建築』二〇一五年月評
一月 世界を少しずつ善くしていくこと
二月 非施設型建築をめぐって
三月 図式と図式を超えるもの
四月 空間をチューニングするということ
五月 こどもたちのための空間とは
六月 一般の人は建築のなにを見ているのか
七月 都市のような建築
八月 マクロから見るか、ミクロから見るか
九月 チューニングがチューニングを超えるとき
一〇月 不一致が不一致のまま共存する箱
一一月 箱が意識から消える
一二月 世界の外に立つということ
第6部 建築をバラバラなモノとコトに向かって開くこと
1 誰が群盲を嗤えるか
2 現実を生け捕りにするには
3 立原道造のヒアシンスハウス
4 三次市民ホール
5 土壌のデザインが建築になる世代
著者:青木淳
出版社:NTT出版
サイズ:四六判
ページ数:269
発行年:2018.05

