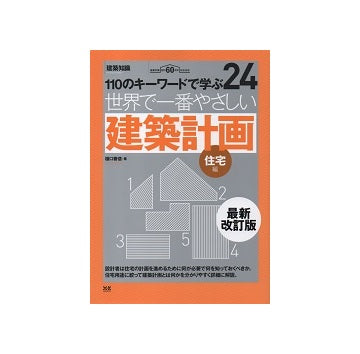
世界で一番やさしい建築計画 住宅編 110のキーワードで学ぶ24 最新改訂版
設計者は住宅の計画を進めるために何が必要で何を知っておくべきか。住宅用途に絞って建築計画とは
何かを分かりやすく詳細に解説。
■目次
・第1章 建て主と設計者の関係
住宅の建築計画とは/設計者の役割/建て主を知る/建て主の暮らし方拝見
家族構成や関係を読み取る/生活感覚を身に付ける/家ができるまでの費用
工事費の目安を立てる/予算の配分/設計量の考え方/様々な補助金の活用
つくり過ぎない家がよい/街の風景になる家を目指す
建築家の住宅に学ぶ 1「私たちの家II期」1978年 林昌二+林雅子
・第2章 実感力や観察力を養う
スケール感を身につける/自分の基本寸法を身に付ける
材料の特性を知る-木/材料の特性を知る-石・土/材料の特性を知る-金属
材料の特性を知る-モルタルとコンクリート
材料の特性を知る-ガラス・ポリカーボネート/工事現場を体験する
住宅を体験する/いろいろな建築を体験する/手を動かそう
色をコントロールする/身近な街並みを意識する/身近な樹木に関心を持つ
情報を活用する
建築家の住宅に学ぶ 2「菅野ボックス」1971年 宮脇檀
・第3章 敷地を知る
住宅に適している土地とは/敷地を読む/敷地条件を調べる
敷地形状を把握する/建物の規模制限/敷地と地盤の調査
設計の手がかりは敷地から
建築家の住宅に学ぶ 3「園田邸」1955年 吉村順三
・第4章 建築計画のポイント
アプローチはできるだけ長く/玄関は家の顔か単なる入り口か
トイレの位置は重要/浴室はくつろぎの場/洗濯は干して仕舞うまで考えて
勝手口とサービスコートはあると便利/キッチンは住まいの司令塔
ダイニングは家族が集う場/居たくなるリビングをつくる
接客のヒエラルキー/予備室としての和室/子供室を考える
寝室は寝るだけの部屋か/家事・書斎コーナーはあると便利
家事動線を考える/収納場所は適材適所/縁側的空間の復権
階段の楽しみ/開き扉か引き戸か/地下室の効用
屋上を上手に利用するには/通風は住まいの要
自然光の取り入れ方で空間の質は変わる/上からの光の取り込み方
証明は適度に明るく、適度に暗く/高齢者や幼い子供への配慮
ぐるぐるまわれる家/広さについて考える/庭を配置する
カーポートは建物と一体で考える/樹木は家とともに育つ
建築家の住宅に学ぶ 4「私の家」1954年 清家清
・第5章 基本計画を立てる
エスキースを描く/住宅のタイトルを考えよう
住宅の諸機能を図式化する/生活行為からカタチを考える
周辺環境と敷地の模型をつくる/ヴォリュームを敷地模型に置く
カタチの組み合わせ/平面で部屋のつながりを考える
断面で部屋のつながりを考える/移動をシミュレーションする
全体構成を調整するための方法/開口部の配置の仕方
内部仕上材を決める/外部仕上材を決める/構造の考え方-木造
構造の考え方-RC造・鉄骨造/設備の考え方
設備もカタチに影響する/住宅の基本性能からカタチを考える
増築・減築への対応/仕切りのカタチ/建て主へのプレゼンテーション1
建て主へのプレゼンテーション2
建築家の住宅に学ぶ 5「コアのあるH氏のすまい」1953年 増沢洵
・第6章 実施設計図を描く
伝達手段としての図面/図面作成の方法-手描きとCAD
実施設計図面の記載ルール/工事の種類を意識する
配置図を描く/平面図を描く/立面図を描く/断面図を描く
矩形図を描く/階段詳細図を描く/その他の図面を描く
設備概要図を描く/建築士法と建築基準法
確認申請図面の要点-一般図/確認申請図面の要点-構造・設備ほか
建築家の住宅に学ぶ 6「聴竹居」1927年 藤井厚二
・第7章 住宅の実現
施工者の探し方・選び方/見積依頼と見積精査/工事監理の内容
検査と引渡し/完成後の保守管理/建て主との付き合いは続く
・本書の内容と構成 あとがきに代えて
・引用・参考文献
著者:樋口善信
出版社:エクスナレッジ
サイズ:B5
ページ数:239
発行年:2020.04

