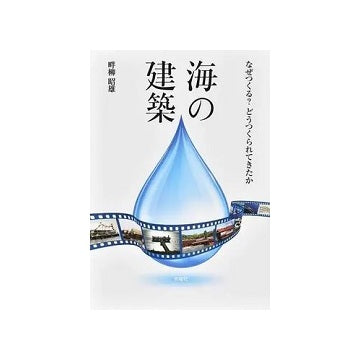
海の建築 なぜつくる?どうつくられてきたか
海の上に祀られる日本の神社、世界中に見られる水上居住など、海の建築は何のために、どうつくられてきたのか。海と建築との関係を系譜的に整理し、その出現の理由や、歴史的、技術的、思想的な経緯について振り返る。
海から来る。海へ帰る。
固定から移動へ、不動から可動へ。
海に呼ばれ、海にこたえた建築の意味の歴史。
■目次
第1章 海と建築と船の関係性
海流が運んだ建築文化、陸に上がった船、船から建築へ
第2章 船に魅せられた建築家たち
刳舟から構造船へ、建築家と船、コンクリートで船をつくる
第3章 清盛と海と建築
海と厳島神社、厳島信仰と神社の創建、平清盛の大造営、福原の築島
第4章 なぜ海に建てられるのか
海の上の建築、土地がない、海の上に建てたい、土地が海に沈んだ
軟弱な地盤、博覧会の開催、戦争時の海軍軍事施設、浮かぶ人工海水浴場
第5章 海と陸との関係性を示すもの
海岸線と汀線、海抜・標高・日本水準原点、験潮場と検潮所
第6章 建築家が描いた夢・海上都市
海の上をどう使うか、東京湾に描かれた海上都市構想
大高正人の東京湾海上帯状都市構想、東大・丹下健三研究室の「東京計画1960」
菊竹清訓の「東京湾計画1961」
おわりに 浮かぶ建築の追求、海と建築の関係を振り返ると
著者:畔柳昭雄
出版社:水曜社
サイズ:A5
ページ数:224
発行年:2021.12

